粉薬を嫌がる小さな子どもに飲んでもらうためのコツ
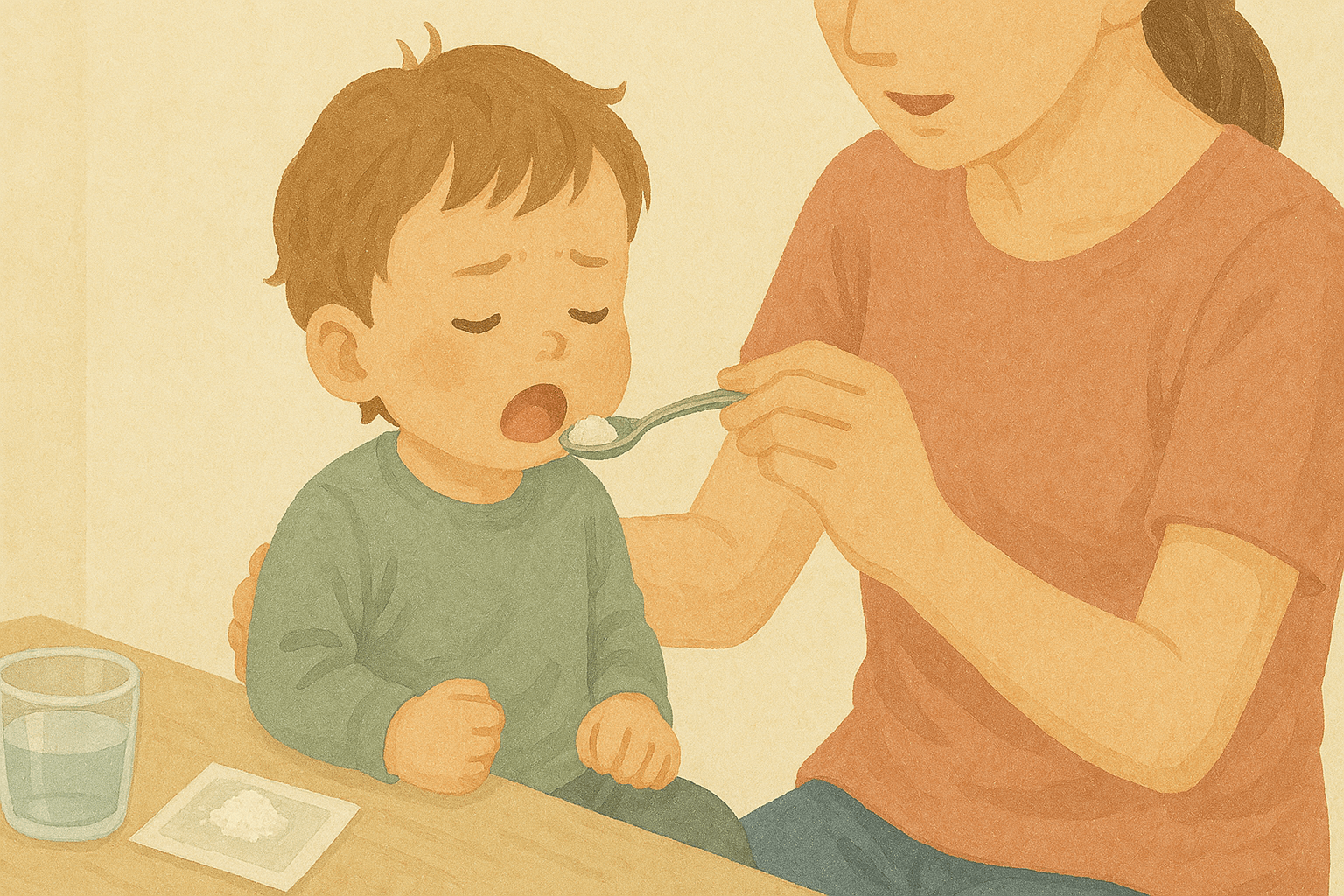
小さな子どもに薬を与えるのは、多くの保護者にとって悩ましい課題のひとつです。特に粉薬は苦みが強かったり、ざらざらした食感が子どもの不快感を引き起こしたりするため、上手に飲ませるには工夫が必要です。
この記事では、年齢別・薬の種類別に、小さな子どもに薬を飲ませるための効果的な方法やポイントを詳しく解説します。薬の種類によって飲ませ方が異なるため、子どもの年齢や好みに合わせて最適な方法を見つけましょう。
年齢別の子どもにお薬を与える工夫を紹介
新生児・乳児期(0〜1歳未満)
この時期の赤ちゃんは、味覚が発達途上にあり、比較的薬を受け入れやすい傾向があります。ただし、誤嚥(ごえん)に注意し、必ず上体を起こした状態で薬を与えることが重要です。
お薬を飲ませる際は、以下の点を注意します。
- 抱っこするか上体を起こした姿勢で与える
- 横向きにした姿勢で与えない
- 泣いているときや満腹時は避ける
- ミルクや母乳に薬を混ぜない(ミルク嫌いの原因になることがある)
お薬を服用させる工夫としては以下の通りです。
指を使って飲ませる
粉薬に水を数滴加えてペースト状にし、清潔な指に乗せて頬の裏側や上あごに塗る方法です。舌に触れると苦みを感じやすいため、なるべく舌に触れないように素早く行うのがポイントです。与えた後は、少量の水やぬるま湯を飲ませて、口内に残った薬を流し込みましょう。
スポイトを使って飲ませる
薬を少量の水で液状に溶かし、スポイトを使用して赤ちゃんの口の脇から少しずつ頬の内側に流し込む方法です。赤ちゃんの呼吸のリズムに合わせてゆっくりと少量ずつ入れることが大切です。
哺乳瓶の口を使って飲ませる
薬を少量の水やぬるま湯で液状にして、哺乳瓶の乳首に入れて吸わせる方法です。この方法では、薬が乳首に残らないよう、投与後に少量の水やぬるま湯を追加して飲ませることが重要です。普段使用している哺乳瓶ではなく、薬用に別の哺乳瓶を用意するとよいでしょう。
幼児期(1〜5歳)
この時期は味覚が発達し、自己主張も強くなってくるため、薬の服用に最も抵抗感を示す時期とされています。個人差が大きいため、子どもの好みに合わせた方法を選ぶことが大切です。
- 子ども自身に選ばせる(スプーン、コップ、ストローなど)
- 空腹時に与えるとスムーズなことが多い
- 強制せず、飲めたときには褒める
- 基本的には薬を単体で水やぬるま湯と一緒に飲む習慣をつける
①スプーンを使う方法
スプーンの上で薬を少量の水やぬるま湯に溶いて、まず1回飲み込ませた後、すぐに水や白湯を飲ませます。最初から多めの水で溶かすと、飲み終わる前に薬の苦みが出たり、量が多くて飲みきれずに薬を飲み残す可能性があるので注意が必要です。
②食品と組み合わせる方法
どうしても飲めない場合は、アイスクリーム、ヨーグルト、ジャム、プリンなどに混ぜると飲みやすくなることがあります。ただし、薬の種類によっては食品との相性が悪いものもあるため、事前に薬剤師に相談することが重要です。
③服薬補助ゼリーを使う方法
「おくすりのめたね」などの服薬補助ゼリーを使用すると、薬の苦みや粉っぽさを感じにくくなります。特に、ゼリーで薬を挟むように上下に配置すると、薬が直接舌に触れにくくなり飲みやすくなります。
学童期(6歳以上)
この時期になると理解力も高まり、薬の必要性を説明すれば比較的飲みやすくなります。また、口腔内崩壊錠など、飲みやすい剤形の薬も選択できるようになります。具体的な工夫は以下の通りです。
- 薬を飲む理由や効果を分かりやすく説明する
- 自分で管理する練習をさせる
- 飲み方を自分で選ばせる
小さな子どもに向けたお薬服用のコツ
服用のタイミング
薬の服用タイミングは効果に影響します。特に指示がない場合は、以下のポイントを参考にしましょう。
- 授乳・食事の前でも服用可能なケースが多い(空腹時の方が飲みやすいことがある)
- 1日3回の場合は、朝・昼・夕と約5〜6時間間隔が目安
- 服用時に寝ている場合は無理に起こさず、起きたときに飲ませる
上手に飲ませるための雰囲気づくり
子どもが薬を飲むことに対して前向きになるための環境づくりも重要です。特に無理やりお薬を飲ませると、「お薬を飲むことが怖いこと」と認識するようになります。以後、子どもがお薬を飲むことに強い拒否感を示すことになりかねませんので注意しましょう。
- 薬を飲む意義を子どもの理解度に合わせて説明する(「ばい菌をやっつけて、早くお友達と遊ぼうね」など)
- 飲めたときは必ず褒める(「ちゃんとお薬飲めたね」「偉いね」など)
- 兄弟やお友達が飲んでいるところ、両親が楽しそうに飲んでいるところを見せる
- シールやちょっとしたご褒美で前向きな姿勢を育む
- 無理強いせず、雰囲気が悪くならないよう注意する
やってしまうとお薬が苦手になること
小さな子どもにお薬を飲ませる時に、絶対にやってはいけないけれど、やりがちなこともあります。これらをやってしまうと、お薬を強く拒否するだけではなく、食事を取らなくなる可能性があります。
母乳やミルクに混ぜる
薬を母乳やミルクに混ぜると、以下のようなリスクがあります。
- 薬の味の違和感で母乳やミルクを摂らなくなる可能性がある
- ミルクを飲み残すことで薬の全量を投与できないことがある
- ミルク・母乳は小児の主な栄養源であり、薬の味でミルク嫌いになると困る
他の薬との不適切な併用や混合
薬同士の併用は薬の効果に影響を与える可能性があります。また、混ぜると味が変わり、嫌がられる可能性もあります。
新しい薬を始める前には、医師や薬剤師に相談することが重要です。また、薬剤師の服薬指導で指示されていない服用方法は避けましょう。
酸性の飲料と混ぜる
粉薬をジュースやスポーツドリンクなどの酸性飲料と混ぜると、以下のような問題が生じる可能性があります:
- ジュースの酸性で粉薬のコーティング剤が溶け出し、苦味が増す
- 成分が反応して効き目が弱くなったり、逆に強くなったりすることがある
特にマクロライド系抗生物質(クラリスドライシロップなど)は、酸性飲料と混ぜると苦味が出現するため注意が必要です。
困ったときの対処法
薬を吐いてしまったとき
服用してからの時間と吐いた量によって対応が異なります。
- 服用後10分以内であれば、再び服用させる(全量吐き出してしまった場合)
- 30分以上経過していれば、体内に入った薬が吸収されている可能性があるため、様子を見る
判断に迷う場合は、医師や薬剤師に相談しましょう。
薬を飲み忘れたとき
気づいたらできるだけ早く飲ませますが、次の服用時間が近い場合は、以下を目安に対応しましょう。
- 1日3回の薬:次に飲む時間まで4時間以上空ける
- 1日2回の薬:次に飲む時間まで5時間以上空ける
- 1日1回の薬:次に飲む時間まで8時間以上空ける
医師や薬剤師に相談しよう
どうしても粉薬を飲めない場合は、一人で悩まず医師や薬剤師に相談しましょう。以下のような相談ができます。
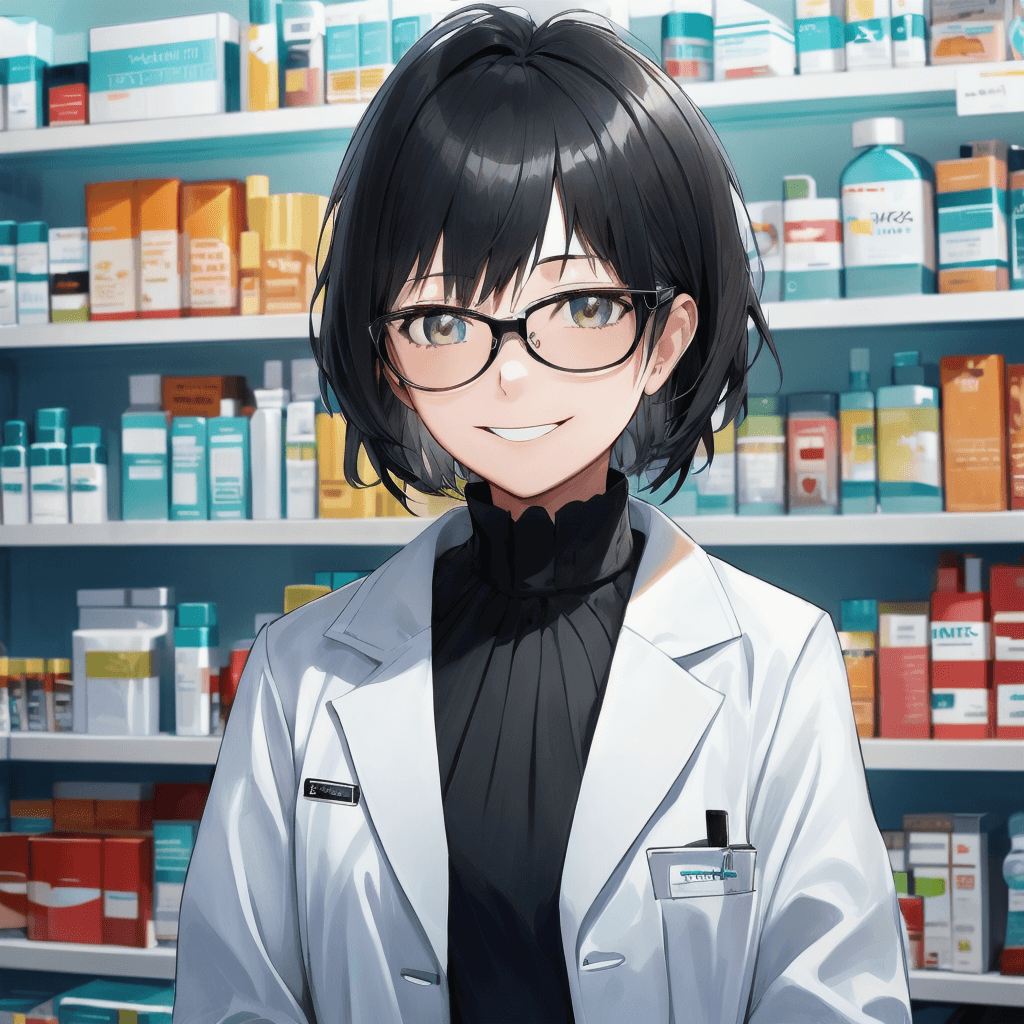
もちろん、お薬のお受け渡しをしたのが、ハニュウ薬局なら、お気軽にご相談ください。
まとめ
小さな子どもに粉薬を飲ませることは容易ではありませんが、年齢や薬の種類に応じた適切な方法を選ぶことで、負担を軽減できます。重要なのは、強制せず、焦らず、工夫を重ねながら子どもが粉薬に対して前向きな姿勢を持てるようサポートすることです。
粉薬を与えるのに悩んだら、医師や薬剤師に相談することをためらわないでください。専門家のアドバイスを受けながら、子どもに最適な服薬方法を見つけていきましょう。





